
行政書士 中島北斗
この記事では、ドローン許可の飛行条件である「補助者の配置」「補助者が不要なケース」「立入管理措置の具体例」について解説いたします。この記事を読めば、適法にドローンを飛行することができるようになります!
2022年11月10日、立入管理措置について新しい考え方が追記された審査要領と飛行マニュアルが公開されました。
それまでは「立入管理措置」=「補助者の配置」のみでしたが、立入管理措置を明示することで補助者の配置が不要となりました。
ドローンユーザーにとっては、嬉しい規制緩和の改正です。
立入管理措置とは「ドローンの飛行経路下に第三者が入らないようにする措置」
航空法において、特定飛行を行う場合は立入管理措置が必要となります。(レベル4飛行を除く)
そして同法によると「立入管理措置は、ドローンの飛行経路下において第三者の立入りを管理する措置であって国土交通省令で定めるもの」とされております。
そして、国土交通省令では「①補助者の配置、②立入りを制限する区画の設定、③その他の適切な措置」と定めれています。
これだけではわかりにくいため、航空局の解釈通達では以下のように分解されております。
| 立入管理措置 | 詳細 |
|---|---|
| ①補助者の配置 | 飛行経路下の監視及び口頭警告 |
| ②立入りを制限する区画の設定 | 関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による立入管理区画の明示 |
※③その他の適切な措置については後述のレベル3、レベル3.5の項目を参照ください。
つまり②立入管理区画を明示できれば、①補助者の配置は不要となります。
飛行経路下=飛行経路直下+落下分散範囲
飛行経路下とは、ドローンの真下だけではなく、ドローンの墜落が想定される範囲内も含まれます。
落下分散範囲の計算方法は法定されておりませんが、リーガライト行政書士法人のeラーニングを導入しているドローンスクールで詳しく学ぶことができます。
ここからは申請別に立入管理措置について詳しく確認していきましょう。
【包括申請】立入管理措置の具体例
包括申請において、一般的な立入管理措置は「①補助者の配置」です。
もしも「②立入管理区画の明示」で立入管理措置を行う場合、具体的な明示の方法は、航空局飛行マニュアルに記載があります。
ここでポイントになるのは、「第三者の立入りを確実に制限できること」です。
確実に制限ができれば、立ち入ったかどうか判断する必要がないため補助者は不要というロジックです。
たとえば、関係者以外立ち入ることができない工場や塀で囲われた住宅などは、確実に制限可能といえるでしょう。
逆に、第三者の立ち入りが可能性として捨てきれず、立ち入った場合に飛行を中止するケースの場合は、立ち入ったかどうかの判断が必要なため、従来通り補助者が必要となることに注意しましょう。
【レベル3】立入管理措置の具体例
レベル3飛行は「無人地帯での補助者を配置しない目視外飛行」です。
ただ上記包括申請の目視外飛行でも、立入管理区画の明示を行えば補助者は不要となりますが、それはレベル3飛行に当たるでしょうか。
結論から申し上げますと、「第三者の立ち入りを確実に制限できる補助者なしの目視外飛行」はレベル3飛行には該当しません。
なかなか解釈が難しいのですが、一言でいうと、レベル3飛行とは「第三者の立ち入りが可能性として捨てきれない補助者なしの目視外飛行」となります。
本改正前は「フェンスで囲われた工場内での補助者なし目視外飛行」も「離島間での補助者なし目視外飛行」も一緒くたにされていましたが、現在はそれぞれ別の扱いとなっています。
| 【包括申請】 第三者の立ち入りを確実に制限できる補助者なし目視外飛行 | 包括申請でも補助者なしで飛行可能 (例:フェンスありの工場内) |
| 【レベル3】 第三者の立ち入りが可能性として捨てきれない補助者なしの目視外飛行 | レベル3飛行に該当するため、飛行場所を特定した申請が必要 (例:離島間、河川上) |
以上を踏まえ、レベル3飛行で求められる立入管理措置の具体例は以下のとおりです。
【第三者が存在する可能性が低い場所が前提】
・インターネットやポスター等による周知
・第三者が存在する可能性を排除できない場所(道路、鉄道等)には、看板等を設置
※上記以外にも立入管理区画の性質に応じて航空局と調整。
【レベル3.5】立入管理措置の具体例
2023年12月26日「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」の改正で「レベル3.5飛行」が認めらるようになりました。
レベル3.5飛行とは、「第三者が立ち入る可能性が低い場所において、機体カメラで飛行経路下に第三者がいないことを確認することで、補助者を配置せずに目視外飛行を行う方法」です。
レベル3で求められていた看板等での周知や設置が不要になり、自由な飛行が可能となります。
ただし、立入管理措置が不要というわけではありませんので、注意しましょう。
レベル3飛行で求められる立入管理措置の具体例は以下のとおりです。
【第三者が存在する可能性が低い場所が前提】
・機体カメラで飛行経路下に第三者がいないことを確認しながら飛行
【レベル4】立入管理措置の具体例
ここまで包括申請→レベル3→レベル3.5の立入管理措置の具体例を見てきました。
最後にレベル4の立入管理措置について考えてみましょう。
結論から申し上げると「レベル4飛行」は立入管理措置は不要です。
そのため、一等技能証明(国家ライセンス)+第一種機体認証+個別申請が必要になっています。
まとめ
以上、ドローン飛行における立入管理措置について解説しました。
許可を取得しても注意が必要!
ドローンの許可承認を取得した場合であっても、意外と多くの注意事項が存在します。
わかりやすい項目ですと「補助者の配置規定」「プロペラガードの装備規定」などですが、細かい項目にも触れると「人口集中地区での夜間飛行」なども禁止されていることがわかります。
その他にも「禁止されている飛行場所・飛行方法・許可の組み合わせ」、「飛行可能風速の規定」など航空法、審査要領などを隅々まで確認しなければわからない項目も数多く存在します。
このような事項を知らなかったことにより航空法を犯してしまう可能性もありますが、逆に全貌がわからず飛行を躊躇してしまう方も多いかと思います。
そのようなことがないよう当事務所では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。
申請時のデータを一式お渡ししているため、1年目はしっかりとした知識・申請書で許可を取得し、2年目以降はご自分で申請される方もいらっしゃいます!
料金やサービス内容についてはこちらから!
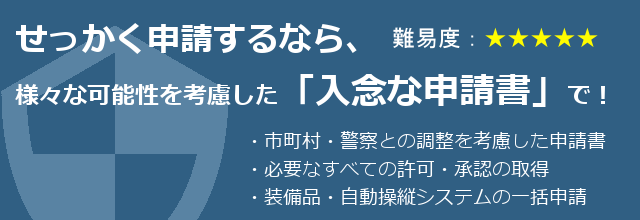
このページをシェアする

執筆者:
行政書士 中島北斗
ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は9,000件、相談実績は11,000件、また50校を超えるドローンスクールの顧問をしています。
SNS「@ドローン法律ラボ」始めました!
ドローンに関する法律をいち早くお届けするため、各種SNSを始めました!
フォローしていただけると、ドローン法律に関する最新情報が手に入ります!
ドローン法務ラボ_マスター|航空法の考え方やDIPSの操作方法など、長尺の解説動画をメイン発信中!
ドローン法務ラボ|航空局の動向、改正情報、ドローンニュースなどをテキストベースで発信中!発信内容はFacebookと同様です。
ドローン法務ラボ|航空局の動向、改正情報、ドローンニュースなどをテキストベースで発信中!発信内容はX(旧Twitter)と同様です。
ドローン法務ラボ_ライト|これからドローンを始めたい方やドローンに少しだけ興味がある方向けの動画をメインに発信中!







