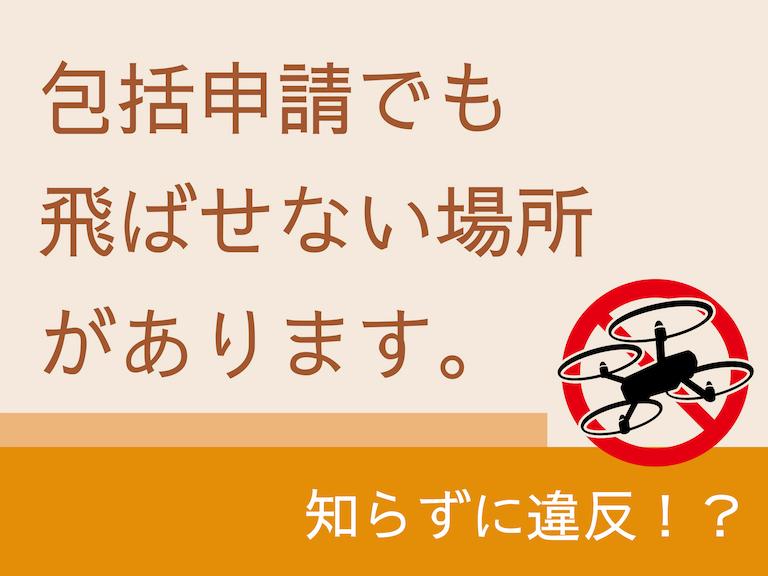ドローンには安全性や情報収集力を高める便利なアクセサリー、飛行ソフトがたくさんあります。
そのようなものを利用した場合、改造になるかというご質問はよくお受けいたします。
これから、ドローン申請における「改造基準」について説明を致します。
本記事は国交省を批判する内容ではありません。いままでの国交省の考え方は「迅速・安全」という視点から評価できますし、これからの考え方も「審査の公平性」という視点から評価できます。
いずれにしてもドローン許可制度自体、過渡期であるためちょうどいい具合を模索している状況ではないでしょうか。
いつも丁寧に、また最新の情報も教えてくださる国交省の方々には本当に感謝しております。
結論:機体メーカーが国交省に申請した「機体」と「そのオプション品」以外は、改造扱い
国交省への申請の際、申請する機体が「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当する場合は、一部機体写真や運用限界等を省略することができます。
省略できる機体として国交省に認めてもらうには、メーカーが機体情報や飛行方法等をまとめ、国交省に申請をする必要があります。
ただし、そのようにして国交省に認められた機体であっても、メーカーが国交省に申請したオプション品以外を利用する場合は、それを利用した状態では認めていないとなり、「改造機体(資料の一部を省略できない機体)」となります。
つまり、例えば「DJI製の機体」に「DJI純正のアクセサリー」を利用する場合も、「改造申請」が必要になるケースがあるのです。
ちなみにオプション品にはソフトウェアも含まれます。
改造機体・改造申請ではなく、確認外機体・確認外機体申請という表現の方がわかりやすいようにも感じます。
メーカー純正品を利用する場合は、改造ではないのでは?
実はいままでは上記のとおり、「メーカー純正品を利用する場合は改造ではない」という判断でした。
しかしながら、2020年9月、以下のような通達が国交省よりありました。
以前よりINSPIRE2の場合プロペラガードを装着している写真を添付すれば「改造していないHP掲載機」で「プロペラガードを装備している。」としてまいりましたが、この度C項がないHP掲載機が「プロペラガードを装備している。」とする場合はすべて「改造しているHP掲載機」の形態で申請していただくことになりました。
※国交省補正内容抜粋
つまり、メーカー純正品を利用する場合も、国交省が確認していなオプション品を利用すると、改造になりますよ!ということです。
上記について国交省に問合せをしたところ、いままでは審査要領に忠実な判断ではなかったので、公平性・透明性のため、厳格にしていくとのことでした。
事実、DJIから国交省に、INSPIRE2のプロペラガードの申請はありません。
しかしながら、今までは安全性・迅速な許可交付という観点からすこし柔軟な対応をしていたのではないでしょうか。
ただDJI以外のメーカーやDJI以外を利用する申請者の立場から見れば、「私たちは改造扱いになるのに」と思ってしまうのも納得できます。
どちらも良い悪いは難しいですが、事実として、このように取扱が大きく変わったということをお伝えいたします。
メーカーが国交省に申請した「オプション品」はどこで確認できる?
このように機体メーカーが国交省に申請した「機体」と「そのオプション品」以外は、改造扱いとなると、「メーカーが国交省に申請した「オプション品」はどこで確認できる?」と疑問になります。
機体自体は「資料の一部を省略することができる無人航空機」はここで確認できます。
ソフトウェアに関するオプション品も一部上記資料で確認できます。
しかしながら、ハードに関するオプション品の記載はどこに…
そう思い、国交省に問合せを致しました。
すると、現時点では確認したオプション品は国交省本庁しか知らない。実際に審査する国交省地方航空局審査官はどの部品が改造になるかわからない。ということがわかりました。※2020年9月時点
今後、「資料の一部を省略することができる無人航空機」に記載する予定とのことでしたが、今のところ確認はできません。
つまり改造になるかどうかは国交省本庁に聞くしかないのが現状です。
2023年7月追記:ハードに関するオプション品について国交省は回答してくれなくなり、メーカーに問合せをしてくださいという案内に変わりました。
まとめ
経験上、NDフィルターや操縦機Cendence、P4の小さい方のプロペラガードは改造となることが分かっております。
つまり一部プロペラガードを除き、装備品を取り付ける場合は、ほとんど改造となります。
ただSONYのカメラの利用確認がされているDJI機体があったりするので純正外部品だから改造になるということもないのです。
ドローン許可制度は出来立て。我々申請者も一緒に発展させていくという気持ちが大切かもしれません。
※個人的には「資料の一部を省略することができる無人航空機」でかつ安全飛行に影響を与えない改造については、申請書にその部品を装備した状態の機体写真と重量を記載するだけでいいのではないかなーと思っております。今は数グラムの改造でも省略できない機体以上のことの記載を求められているので… 今後申請が増えることを考えると審査官側の負担も軽減できるのでないでしょうか。
本記事は国交省を批判する内容ではありません。いままでの国交省の考え方は「迅速・安全」という視点から評価できますし、これからの考え方も「審査の公平性」という視点から評価できます。
いずれにしてもドローン許可制度自体、過渡期であるためちょうどいい具合を模索している状況ではないでしょうか。
いつも丁寧に、また最新の情報も教えてくださる国交省の方々には本当に感謝しております。